top of page
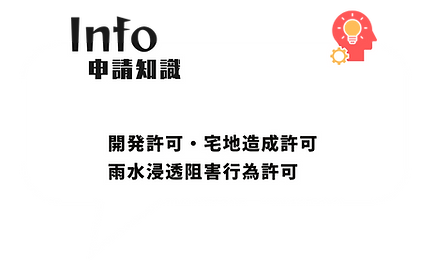


オルタナ都市開発は、主に宅地造成や開発行為に関する企画・設計・申請手続きを専門とする建築設計事務所です。土木工学科出身のスタッフと大手ハウスメーカー設計部での実務経験を持つスタッフにより、分譲地(土地+住宅)の販売を見据えた、機能・安全性・意匠性を兼ね備えた提案が可能です。
開発業者様からは、土地分譲・分譲住宅の販売を目的とした企画設計および申請手続きを、ハウスメーカー・工務店様からは、建築確認申請や宅地造成許可申請の代行、施工図面作成、初期段階の企画設計のサポート業務を承ります。
完成宅地業務対応エリアは、愛知県全域・岐阜県・三重県・静岡県の一部(※詳細は こちら をご参照ください)

bottom of page




